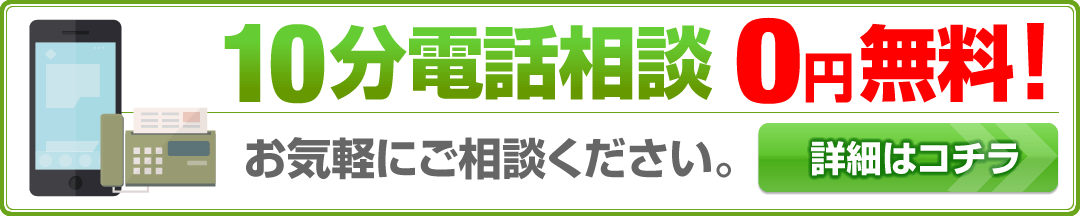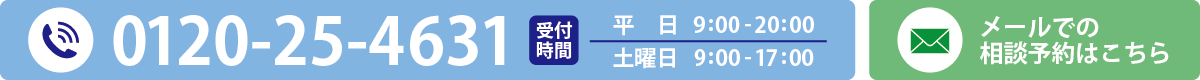多くの経営者は真摯に丁寧に経営に向き合っているかと存じますが、稀に「少しでも会社や家族のために」という思いから、結果的に不正行為にあたる行為をしてしまうケースがあります。しかし、これらの行為は、時には刑事罰や、財産を失うといった重いペナルティが科されるだけではなく、会社の破産手続きにも影響し、従業員や取引先などの債権者にも更なる迷惑をかけてしまうことになりかねません。
何が不正にあたり、どのようなリスクがあるのか、主だったものをご紹介します。
①偏頗弁済
親族や友人、取引先など、一部の債権者にだけ、弁護士に破産手続きを依頼する直前、あるいは裁判所に破産申立する直前に借金の返済や支払いをする行為です。
これは「すべての債権者を平等に扱う」という破産の原則に反します。
②不適正な財産の処分
破産手続を行うと決める直前付近で、相場よりかなり安価で在庫や自動車や不動産や機械・工具類などの会社の資産を売却する行為です。
※上記①②は会社の財産を不当に減少させたとして問題視され、破産管財人によって返済や売却行為が取り消される(否認される)ことがあり得ます。あるいは、財産の処分の相手方は、管財人からお金を回収される可能性もあります。
良かれと思ってした行為でも、かえって、関係者に迷惑をかけることになってしまいます。
③財産を隠したり名義変更したり壊したりすること
会社名義の預金や自動車や不動産などの会社の資産を、代表者の親族などの他者の名義に変更したり、隠したり、あるいは壊したりする行為です。
④帳簿や書類を隠したり、偽造や改ざんする行為
報告書類や提出資料に嘘の情報を書いたり、財産を少なく見せる目的などで帳簿を操作したりする行為です。
⑤説明を拒んだり、嘘の説明をすること
※上記③~⑤の行為は、行うと詐欺破産罪として処罰されたり、拘禁刑や罰金などの刑事罰が科されるおそれがあります。
悪意がなく行った行為でも、結果として不正と判断される場合もあるかもしれません。悩んだときはまずは専門家(弁護士)にご相談されることをお勧めします。
なにより専門家(弁護士)に「すべて正直に話す」ことが最大の防御であり、それが経営者や家族や従業員を守り、皆で早い再スタートを切ることにも繋がります。